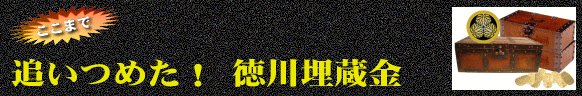 |
 |
■やったぞ! ついに坑口が開いた 単純でしんどい作業が続いたためか、9月に入ってからは参加者が少ない。したがって、一人ひとりが担う労働量も多くなるし、その分危険度も増す。しかし、坑口が手の届くところにあるのはわかっているのだから、ここが踏ん張りどころだ。 雨上がりの9月20日、斜面がゆるみ、大規模な崩落が起こった。身の危険はなかったが、木枠と斜面の間に空間ができ、再び大崩落が起きてもおかしくない。頭上の軽く1トンは超えそうな大きな岩もずり落ちてきた。 そんな中、少人数で必死に崩落防止の棚を作り、落ちてきた土砂を土のうに詰めて、上からすき間をふさいでいく。柱ももう1本追加して、全部で8本になった。 そして、9月21日の昼過ぎ、壁をつついた長い棒の先がふっと空間に吸い込まれた。 「開いたぞ!」 歓声が谷間にひびきわたる。首が突っ込めるだけの小さな穴から、今度こそはっきりと、坑道の壁がのぞいていた。 |
|
|||||
|
■いよいよ坑道内へ 岩盤をくり抜いた坑道の立派さに驚く 1週間前に開いた穴は、上から落ちてきた土砂で再びふさがれていた。しかし、人が入れるだけのスペースを確保するのはもうさほど難しいことではない。ただ、中に入ったあとで入り口がふさがれてしまうとたいへんなので、脇を固める工事を慎重に行う。これに1日半を要した。そして最後は、大きな岩を横に真っ二つに割り、上の部分を太い丸太で坑道内に押し込んで、ようやく侵入口を完成させた。 9月27日の午後、まず私を含む3名で坑道内へ。キャップランプをつけたヘルメットをかぶり、手にはLEDライト。そしてロウソクも。酸素の状態を確かめるほかに、坑道の距離を測る目的もあった。昭和3年に金鉱の調査のために入った人の記録によると、坑道はまず坑口からまっすぐ150尺(約45m)続いているという。そこで、ろうそくを5mおきに立てることにした。9本立てれば分かれ道に達する計算だ。 中に入ってみてまず驚いたのは、坑道の立派さ。坑口付近は高さが2m以上、幅も同じくらいある。岩盤をきれいにくり抜いていて、形はほぼ真四角。一部崩れているところもあるが、保存状態は極めてよい。規模は違うが、世界遺産に登録されている石見銀山の龍源寺間歩を髣髴とさせる。観光コースとなっている佐渡金山や伊豆の土肥金山の旧坑道にも匹敵する美しさだ。 |
|||||
| ■萩原翁から聞いていた通りの立て坑が見つかる! ロウソクを9本立てたが、まだ奥まで行き着かない。実際には坑口から60mほど入ったところに分かれ道があった。ここは天井の高さがゆうに5mはある。鉱脈を追って掘り進んだあとだろう。 さて、萩原翁から聞いていた問題の場所は、そこから左へ進んだところにあるはずだ。水がたまった深い井戸のような立て坑……。 「あ、ここか!」 先頭を進んでいた高橋グループの横山幸男氏が叫んだ。左のルートは10mも行かないうちに行き止まりになっていて、そこに澄み切った水を満々とたたえた立て坑があった。身を乗り出してのぞき込んでみたが、水底にあるのは坑木の残がいか昇降用のはしごのようなものばかりで、箱とおぼしきものはない。そりゃそうだろう、これだけ水が透き通っていたら、底に沈めても隠したことにはならない。 「あっ、ここは二重になってる!」 横山氏が再び声を上げた。なるほど、よく見ると、立て坑の底から足もとの方へ向かって横穴が続いている。しかし、足場がないので、その先をのぞき込むことはできない。隠し場所としては最適ではないか。潜って確かめられないこともないが、ここはやはり予定通り水を抜くのが一番だろう。そのための道具がひと月以上前から運び込んである。 |
|
立て坑の水を抜けば、千両箱が姿を現すはず。次回は1週間後、待ちきれない思いだった
 |
 |
 |






